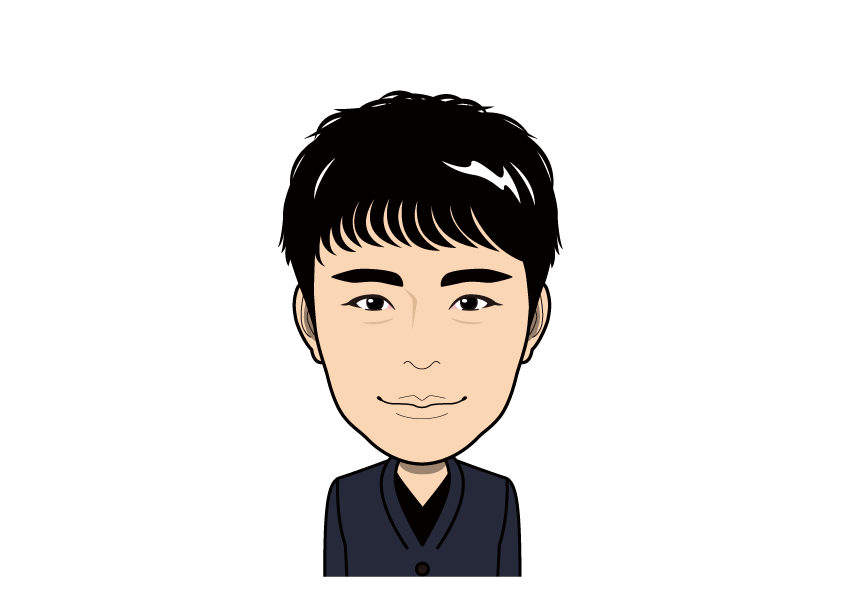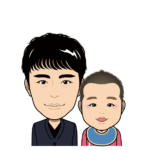いざ玉掛けの資格を取ったとしても技能講習の実技だけでは物足りません。
当記事は玉掛けの基本手順を13の項目に分けわかりやすく説明する内容となってますので玉掛け初心者〜ベテランまでおすすめの内容となっています。
手っ取り早く動画で手順を復習したい人は実技試験対策・動画5選!ご覧ください。
こんにちは元トラッカーのぎん丸です。
玉掛けしてますか?
資格取得後が本番ですからね。
玉掛け技能講習を受講し資格を取ったからには実際にその日から玉掛け作業ができます。
しかし資格は簡単に取れても玉掛け作業は非常に奥深くシビアで習得するには相当な年数及び経験が必要となってきます。
いざ実際に現場で玉掛け作業をするにあたって気をつける事があります。
目次
初心者が守るべき13の手順

資格者証は常に携帯するべし
基本中の基本。
建設現場での新規入場教育時や直接お客さんから提示を求められる場合もあります。
資格者証がなければ作業できませんので常に免許証などと一緒に携帯しておきましょう。
もし資格者証不携帯で玉掛け作業をやっているのが見つかってしまうと、最悪は作業中止、あなただけでなく会社の信用がガタ落ちします。
・「資格者証携帯」よし!
クレーンオペレーターと合図の確認をすべし
作業開始前には必ずクレーンオペレーターと合図の確認しましょう。
合図は手と笛を使っての複合合図をおすすめします。
複合合図については【玉掛合図方法】クレーン作業時は手と笛を使って合図すべし!ご覧ください。
同時にクレーンオペレーターとの打ち合わせでオペさんの性格を見抜きましょう。
性格を見抜く事で合図を臨機応変に変えたり工夫しましょう。
・「合図の確認」よし!
適切な吊り具を選定すべし
あらかじめ吊り具が指定されている場合を除きワイヤーなのかスリングなのか荷を見てから適切な判断をしましょう。
ワイヤー切断荷重表を見て選ぶことがポイントです。
・「吊り具の選定」よし!
吊り具の点検をするべし
建築現場などでは始業前に吊り具の点検が義務付けられています。
不良な吊り具を使用すると事故につながるのでやめましょう。
・「ワイヤー」「スリング」亀裂損傷なし!
荷の重心を見極めるべし
吊り荷は必ずしも重心が真ん中ではありません。
荷によっては重心が記されている事もあるのでよく確認しましょう。
重心を間違えて地切りしてしまうと荷が転倒して大事故に繋がる恐れがあります。
・「荷の重心」よし!
荷の重量を確認すべし
当たり前ですが荷の重量をあらかじめ確認しましょう。
わからない場合はメーカーに直接問い合わせるのもよいでしょう。
重量によって吊り具の選定や玉掛方法も変わってきます。
地切り後にクレーンのオペさんに重量を確認してください。
よくある事ですが実際に吊ってから聞いていた重量と違うことなんてザラにあります(笑)
その為に吊り具は余裕を持って選定しておきましょう。
・「荷の重量」よし!
クレーンのフックの外れ止めを確認すべし
フックに外れ止めをよく確認しましょう。
引用:中古トラック買いたいより
・「フックの外れ止め」よし!
ワイヤー・スリングの重なりがないか確認すべし
ここでようやくフックにワイヤーやスリングをかけます。
その際フックにワイヤーやスリングが重なっていないかよく確認しましょう。
重なってしまっていると均等に荷重がかからなくなり事故の原因へと繋がりかねません。
・「ワイヤー・スリングの重なり」よし!
吊り角度を確認すべし
玉掛をしてワイヤー・スリングを張ったら吊り角度を確認しましょう。
吊り角度が大きくなるほど張力が増加し安全使用荷重が小さくなります。

引用:燃えろ!タマカケ魂より
・「玉掛け」よし!
地切り前、今一度周囲を確認すべし
いよいよ地切りまでいきます。でもちょっと待って!
周囲に人がいないか確認してください。
万が一荷が倒れてしまったら下敷きになって死亡事故になってしまうかも。
※これが「玉掛作業者」の最大リスクです。
事故が起きれば
- 玉掛けしたあなた
- 合図をしたあなた
が罰せられます。
そして構築物や上空に障害物がないかも確認しましょう。
そしていよいよ地切りまでクレーンを巻かせてください。
慎重にゆっくりゆっくりとじんわり巻かせてくださいね。
・「地切り」よし!
地切り後、荷の安定を確認すべし
地切り後、荷の安定は良いか傾いていないかをよく確認してください。
少しでも違和感を感じたら、再び吊りなおしたり玉掛方法を変えてください。
ここで手を抜いたが為にたくさんの事故が発生しています。
時間は掛かりますが慎重に慎重に行きましょう!
・「荷の安定」よし!
まとめ

1.「資格者証携帯」よし!
2.「合図の確認」よし!
3.「吊り具の選定」よし!
4.「ワイヤー」「スリング」亀裂損傷なし!
5.「荷の重心」よし!
6.「荷の重量」よし!
7.「フックの外れ止め」よし!
8.「ワイヤー・スリングの重なり」よし!
9.「吊り角度」よし!
10.「玉掛け」よし!
11.「周囲の確認」よし!
12.「地切り」よし!
13.「荷の安定」よし!
どうでしたか?
熟練者の方々から言わせればいちいちそんな事やってらんないよ!と声が聞こえてきそうですが初心に戻ることは大切なので今一度初心に戻ってみたらどうでしょうか。
おわりに
玉掛け基本手順は参考になりましたか?
実際の現場ではまずこんな手順を踏んでやっている人はいないでしょう。
玉掛け作業の基本中の基本を初心者のうちに身につけることによって、経験を積むにつれて基本が身についている人と自己流、我流でやってきた人とは差が出でくるのです。
基本を知らない人は必ず事故を起こします。
基本を知っている人ももちろん事故を起こします。
実は事故を起こした時に基本が身についている人と身についていない人に差が出る事が多いのです。
その差とは一つの事故が軽度の事故か重度の事故になるかの差です。
先程も述べましたが
事故が起きた時
- その時玉掛けしたあなた
- その時合図をしたあなたが
罰せられます。
玉掛けミスによる事故は死亡事故を含め年間に相当数が実際に起きています。
事故が起きた時、その当事者があなたにならない為にも基本をしっかりと身につけ今後たくさん経験を積んで
熟練の玉掛け師になって下さい。
そしてこの記事を最後まで読んでくれた熟練の玉掛け師の皆さま今一度、初心に戻って明日から安全作業をしてくれたら幸いです。
当ブログではこの記事で紹介した以外にも自身が経験し体験した役立つ情報を発信していますので、講習の合間に以下の記事を参考にしていただければと思います。