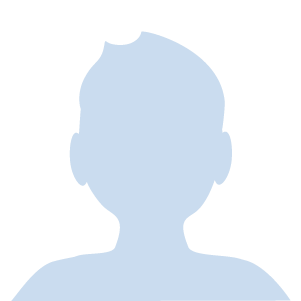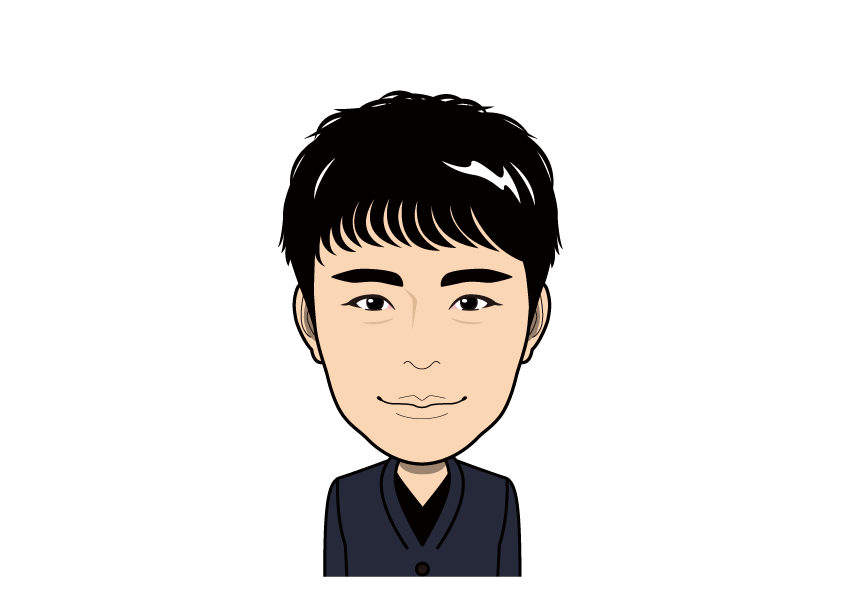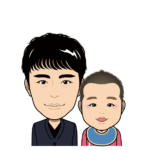労働安全衛生法が改正され2019年2月1日より※一定の作業においてはフルハーネス型の墜落制止用器具を労働者に使用させ、当該労働者に対し特別教育を行うことを事業者に義務付けました。
ちなみに2019年2月1日以降に特別教育を修了していない人が該当業務を行うと法令違反となります。
こんにちは元トラッカーのぎん丸です。
「フルハーネス型墜落制止用器具 特別教育」を受けてきました。
まだまだ業界に精通している身なので該当作業はしないけど興味あるので自腹で特別教育を受けてきました(笑)
特別教育を受けた感想としては猶予期間だの新規格だの生産禁止だの正直よく理解できませんでした(笑)
結論から言うと※一定の作業においては新規格のフルハーネス型墜落制止用器具を使用して作業すれば間違いないってことです。
当記事では特別講習を受けてフルハーネス型墜落制止用器具の知識で大事なポイントをまとめました。
※一定の作業とは
高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところでの作業。
なぜ名称が「墜落制止用器具」に?

従来の安全帯という名称には胴ベルト型(一本つり・U字つり)とハーネス型が含まれていました。
しかし今回フルハーネス型を原則とする主旨から墜落制止機能のないU字つり安全帯を除き、国際規格に合わせ高所からの墜落を制止するために用いる器具として「墜落制止用器具」という名称になりました。
ちなみに今後日本においては現場で従来の呼称である「安全帯」という名称を使うことは問題ありません。
現場朝礼で
なんて違和感ありますよね(笑)
特別教育の対象者

法令で特別教育が義務付けられる対象者
- 高さ2m以上の場所で作業床を設けることが困難なところにおいてフルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務に限られる。
したがって作業床が設けられている箇所での作業に従事している人において特別教育は義務付けられていません。
ちなみに高所作業車のバスケット内は作業床と認められているため特別教育は義務付けられていませんが、高さが6.75mを超える箇所で作業を行う場合はフルハーネス型墜落制止用器具の使用が義務付けられます。
つまり特別教育を受ける必要があるようです・・・。
作業床があるとかないとか言ってますけど、作業床の定義はないので具体的な判断は所轄の労働基準監督署にご相談くださいと国土交通省の質疑応答集に書いてあります。
よって高所作業に少しでも係る人は特別教育を受けるのが無難です。
フルハーネス型が義務化された理由

従来の安全帯(胴ベルト・1本つり)では墜落時に内臓の損傷や胸部圧迫で最悪は死に至るといった名ばかりの命綱で、まったく安全ではないことは昔から危惧されていました。
対してフルハーネス型ならば着用者の肩・腰・腿などの複数箇所で保持できるため墜落時に宙づり状態になったとしても体に与えるダメージがはるかに少ないのです。
高所作業に携わっている人なら従来の安全帯がいかに安全でないかはとっくに気づいていたはずです。
ちなみに欧米諸国ではフルハーネス型がとっくに義務化されていて日本はかなり遅れています。
新規格適合フルハーネス
新規格に適合した代表的な3つのフルハーネス型の墜落制止用器具を紹介します。
一番人気はタジマ製です。
おわりに
個人的には何m以上とか猶予期間とかは関係なしに高所作業に従事する人はフルハーネス型の墜落制止用器具を着用して作業をすべきだと考えます。
昔遊びでユニックで胴ベルト式の安全帯で吊られた時の痛みは今でも忘れません(笑)
実際の高所作業時に不意に墜落したら胴ベルト式では内臓や肋骨はほぼ間違いなくやられるでしょう。
安全でも何でもありません。対してフルハーネス型は着用方法さえ間違えなければ従来の安全帯と比べて衝撃は段違いです。
万が一に備えてあなた自身・家族・会社のためにもフルハーネス型を着用しましょう。
当ブログではこの記事で紹介した以外にも自身が経験し体験した役立つ情報を発信していますので、講習の合間にでも以下の記事を参考にしていただければと思います。