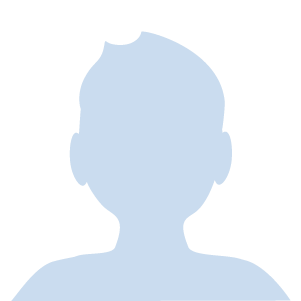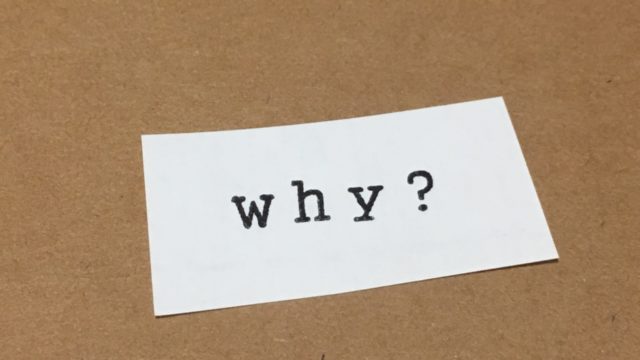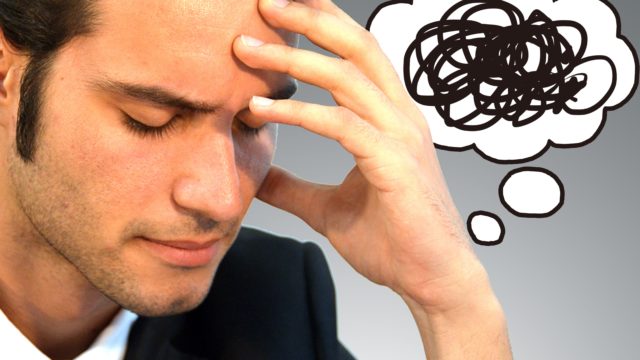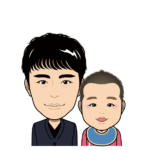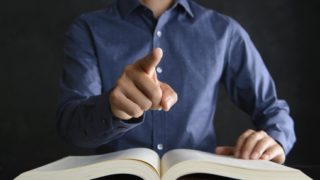元トラッカーのぎん丸です。
当記事では高速自動車国道と自動車専用道路の違いにそれぞれの違いを簡単にわかりやすく紹介します。
実はプロドライバーであるトラック・バスの運転手でも違いを正しく理解しているごく少数しか理解していません。
双方を何気なく高速道路と一つの位置づけとしてくくってしまいがちですが、それぞれの高速道路には特徴があり、予期せぬ違反で切符を切られるケースもあるのでこれを機に学んでおきましょう。
当記事を読んで豆知識を身に付けて、明日から周囲の人にドヤ顔で高速自動車国道と自動車専用道路の違いについて教えてあげましょう。
高速自動車国道とは?

自動車専用の出入口であるIC(インターチェンジ)を設置、制限(料金所)し日本全国にまたがり展開している高速道路ネットワークです。
首都圏の主な高速自動車国道を紹介します。
- 東名高速道路
- 新東名高速道路
- 中央自動車道
- 関越自動車道
- 東北自動車道
- 常磐自動車道
- 東関東自動車道
- 東京外環自動車道
- 首都圏中央連絡自動車道(圏央道)
簡単に言う距離の長い高速道路の多くが高速自動車国道にあたります。
高速自動車国道は国道なので建設費は原則国費で建設されます。
自動車専用道路とは?
著しく交通量の多い道路の流れをよくするために作られた地域交通用の高速道路です。
高速自動車国道と違い距離が少なくおもに国道周辺に多いのが特徴です。
首都圏の主な自動車専用道路を紹介します。
- 京葉道路
- 保土ヶ谷バイパス
- 第三京浜
- 横浜新道
- 新湘南バイパス
- 西湘バイパス
- 小田原厚木道路
- 箱根新道
- 横浜横須賀道路
- ※首都高速道路
地域密着や観光要素を持つ場所に設置された道路も含まれます。
地域交通のための高速道路なので建設費の一部は地方自治体も負担します。
※意外かもしれませんが首都高速道路は1964年の東京五輪開催を機に都内の渋滞緩和を目的として開通された自動車専用道路です。
高速道路と自動車専用道路の具体的な違い

利用できない車の種類
- ミニカー
- 小型二輪車
- 125cc以下の普通自動二輪車
- 原動機付自転車
- 小型特殊車両(自動車専用道路は可能)
- 事故車をロープでけん引している車(自動車専用道路は可能)
制限速度
高速自動車国道
- 法定速度 100㎞/h(一部区間は110㎞/h)
- 最低速度 50㎞/h
自動車専用道路
- 法定速度 60㎞/h
- 最低速度 規制なし
※豆知識①
ぎん丸がトラックドライバー時代に首都高速湾岸線の横浜ベイブリッジをトラックで走行していた時の出来事です。
走行車線の前方が渋滞気味だったため追い越したところ、なんとフォークリフトが横浜ベイブリッジ上を走行していたのです。
あんな交通量の多い首都高をフォークリフトが走行しているなんて危険極まりない行為だとは思いますが、首都高速道路は自動車専用道路ですので最低速度制限がありません。
ナンバー付きのフォークリフトは小型特殊車両にあたるため法律上は走行できるというわけです。
※豆知識②
東名高速道路などの高速自動車国道で制限速度80㎞/hの標識を見かけますがその標識は本来100㎞/hで走行して良い道路なのに80㎞/hに制限しているという意味です。
一方で自動車専用道路での制限速度70㎞/hや80㎞/hの標識は本来は法定速度の60㎞/hで走行しなければならない道路を特例でその速度を認めているという意味なんです。
通行料金
高速自動車国道
- 普通車の場合1㎞あたり24.6円(一部区間は特別料金)
- ターミナルチャージ利用用料 一回150円
- ※ターミナルチャージとは簡単にいうとICをくぐる初乗り料金
自動車専用道路
- 普通車の場合1㎞あたり12.3円~198.7円(個別路線毎の採算を加味した料金)
- 高速自動車国道と違って地域や観光要素で変わるため料金設定が幅広いのが特徴
おわりに

週末のドライブの話のネタにでもして頂ければ幸いです。
最後に1つぎん丸が言いたいのは高速自動車国道よりも自動車専用道路が圧倒的に覆面パトカーの出現率が高いので注意してください。
その中でも速度制限70㎞/hの自動車専用道路は覆面パトカーの遭遇率は群を抜いています。
首都圏でいうと週末の西湘バイパス・小田原厚木道路・横浜横須賀道路なんて覆面パトカーと白バイのオンパレードで他県ナンバーのレジャー車が数キロおきに速度超過で捕まっていて悲惨な状況です。
伊豆・箱根方面に遊びに行く人は注意しましょう。
90㎞/h以上で捕まります。
楽しいはずの週末が悲惨な週末にならないよう安全運転で行ってください。
最後までご覧いただきありがとうございました。
※初心者ドライバー向けの記事となってますので参考にご覧ください↓